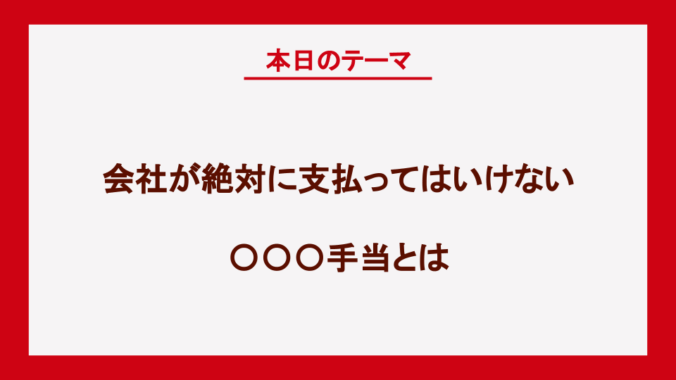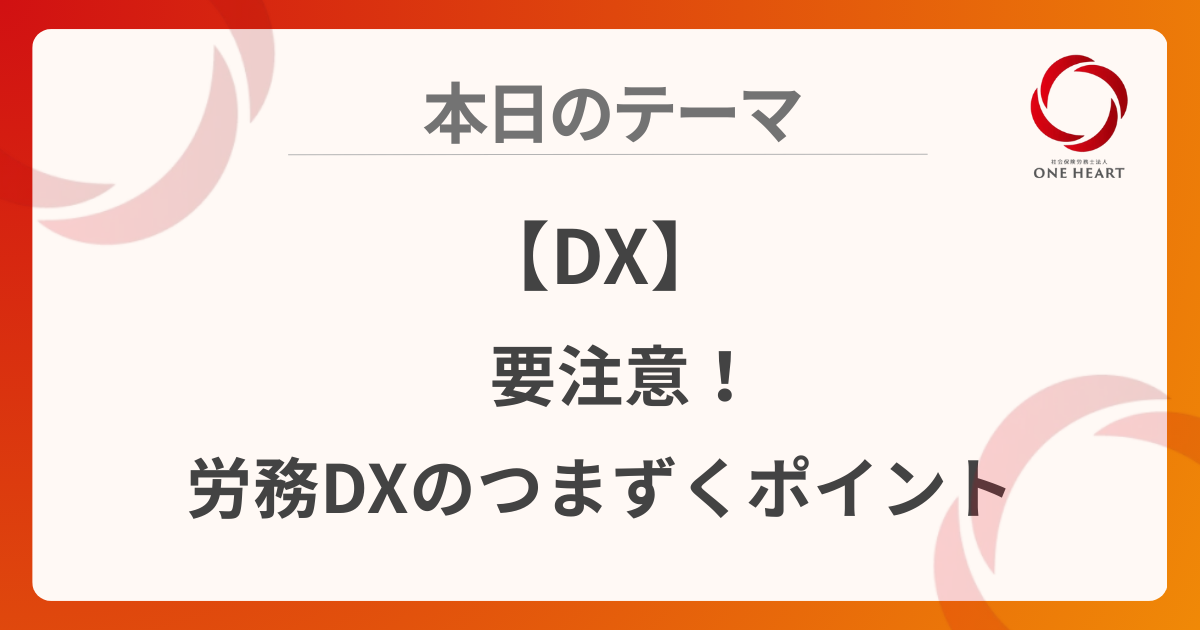
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第112回、第113回の配信をもとに書かれた記事です。
【DX】要注意!労務DXのつまづくポイント(前編)
【DX】どうやって乗り越える?労務DXのつまづくポイント(後編)
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
今回は、社労士に向けて、労務DXを進める上でつまずきやすいポイントを解説します。 DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略で、競争力を高めるために、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、業務そのものや企業文化等を変革することです。
当社は、開業から3年経過し、DXに強い社労士事務所だと認知していただいているのを日に日に感じるようになりました。これから労務DXに取り組む方、現在進行形で苦労されている方は、ぜひ参考にしてください!
労務DXに目覚めたきっかけと、ノウハウの獲得方法
私が労務DXに目覚めたきっかけは、士業関係の勉強会で、SmartHRという労務管理システムを中心としたバックオフィスの事例を聞いたことです。それまで手作業の連続だった業務が、データベースとAPI連携により効率化されることに衝撃を受けました。この経験を基に、開業当初から積極的にクラウドツールを導入し、お客様を支援していきたいと考えるようになったのです。
しかし、最初はノウハウが全く無く、試行錯誤の連続でした。いきなりお客様の情報で実践するわけにもいかないので、最初はSmartHRのアカウントを作り、自分自身をテストユーザーとして招待し、各種設定を試しながらツールの使い方を覚えていきました。勤怠管理システムについても同様に、自ら打刻を行い、様々な機能を試すことでノウハウを得ていきました。このように、まずは自社で実際に使用し、経験を積むことが重要です。
知っておきたい業界によるITリテラシーの違いと、労務DXの進め方
労務DXを推進する上で、業界によるITリテラシーの違いは大きな壁となります。例えば、IT企業ではデジタル化が当然として受け入れられ、クラウドツールの導入もスムーズに進みます。一方で、ITに不慣れな従業員が多い業界では、デジタル化への抵抗感が強い傾向があります。
例えば、福祉業界では、利用者や従業員の多様性に配慮し、デジタル化によって取り残される人が出ないようにという意識を持つ方が他の業界に比べて多いと感じています。一部従来の業務が取り残されるなど、画一的にデジタル化をすることが難しいと、移行するのは大変だと感じました。
他にも、従業員がメールアドレスを持っていないといった、クラウドツールの導入以前の問題に直面することもあります。このように、労務DXは相手を選ぶ側面があるため、いきなり難しい業界からDX化するのではなく、まずはITリテラシーの高い業界や若い従業員が多い企業から始めるのがおすすめです。
労働基準法とクラウドツールのギャップを埋めるには
労働基準法はDXを前提として作られていないため、クラウドツールとの間にギャップが生じることがあります。例えば、就業規則で端数処理を細かく定めていると、クラウドツールの仕様と合わない場合があります。就業規則はその会社独自のルールのため、クラウドツールでできること、できないことを確認し、それに合わせて見直すのがよいでしょう。
具体的には、給与規程において端数処理を定める際には、「給与計算における端数処理は給与計算ソフトの設定に従う」とすることで、ツールの変更や仕様変更にも柔軟に対応できます。また、手当や労働時間の集計方法も、導入予定のツールに合わせて設計することが重要です。深夜労働の賃金計算方法など、ツールによって得意・不得意があるため、事前に確認し、それに合わせた運用を検討しましょう。
既存業務の棚卸と、クラウドツールに合わせた再設計の重要性
労務DXを成功させるためには、現在の業務をそのままデジタル化するのではなく、一度すべてを棚卸し、クラウドツールに合わせて再設計することをおすすめします。中小企業では、明文化されていないルールや例外処理が多く存在することがあり、これらをシステムで再現しようとすると、結果的に手作業が増えてしまう可能性があるためです。
また、クラウドツールは万能ではないので、できないことは諦めるという割り切りも必要です。例えば、法定休日の特定についてです。法定休日とは、労働基準法で定められた休日で、毎週1回以上、もしくは4週を通じて4日以上従業員に対して付与しなくてはならないもので、その日に労働させると35%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
そのため、土日休みの場合は、法定休日を特定せず、土曜日働いたら日曜日が法定休日に、 日曜日働いたら土曜日が法定休日になるというルールにしておくと、会社の人件費は少なくなるため、使用者側には有利と言われています。
しかし、これをデジタル勤怠システムの中でこれを再現しようとすると、人ごと、週ごとに休日を指定していかなくてはいけないため、かえって大変になってしまいます。生産性を高めていく上では、 あえて法定休日を特定し、画一的に処理を行う方が良いでしょう。
労務DX時代に求められる社労士像
労務DXが進んでいくと、社労士に求められる役割も変化しています。以前は、お客様が困った際に直接出向いて、話を聞いてくれる方の需要が高かったのですが、今後は単に人柄が良いだけでは不十分であり、不備のない成果物の提出が必要不可欠となります。
そのため、クラウドツールの仕様を理解し、業務設計に落とし込む能力が重要であり、その上で、法律の基礎を理解し、適切なアドバイスができることも求められます。労務DXは、社労士にとっても大きなチャンスであり、真の実力が試されると言えるでしょう。
まとめ
労務DXは、業務効率化や生産性向上に大きな効果を発揮します。しかし、推進をしていく中で、業界特性やITリテラシーの違い、労働基準法とのギャップなど、様々な課題にぶつかることがあります。その課題を乗り越えるためには、クラウドツールの特性を理解し、それに合わせた業務設計を行うことが重要です。
生産性が高くなればなるほど、設定の正確性や成果物の質も求められていきます。DX推進の波に取り残されず、適切なアドバイスができる知識を身につけて、社労士として共に成長していきましょう。社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
【DX】要注意!労務DXのつまづくポイント(前編)
【DX】どうやって乗り越える?労務DXのつまづくポイント(後編)
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。