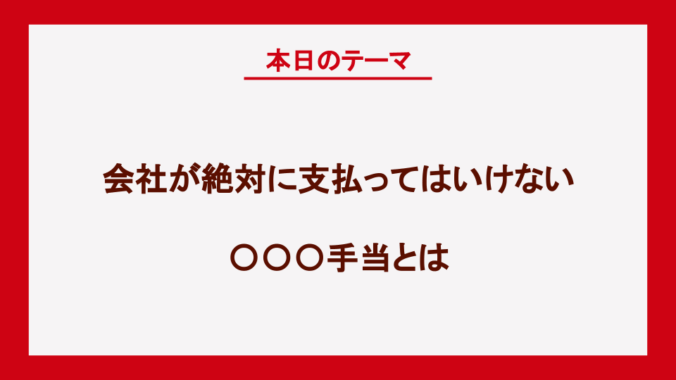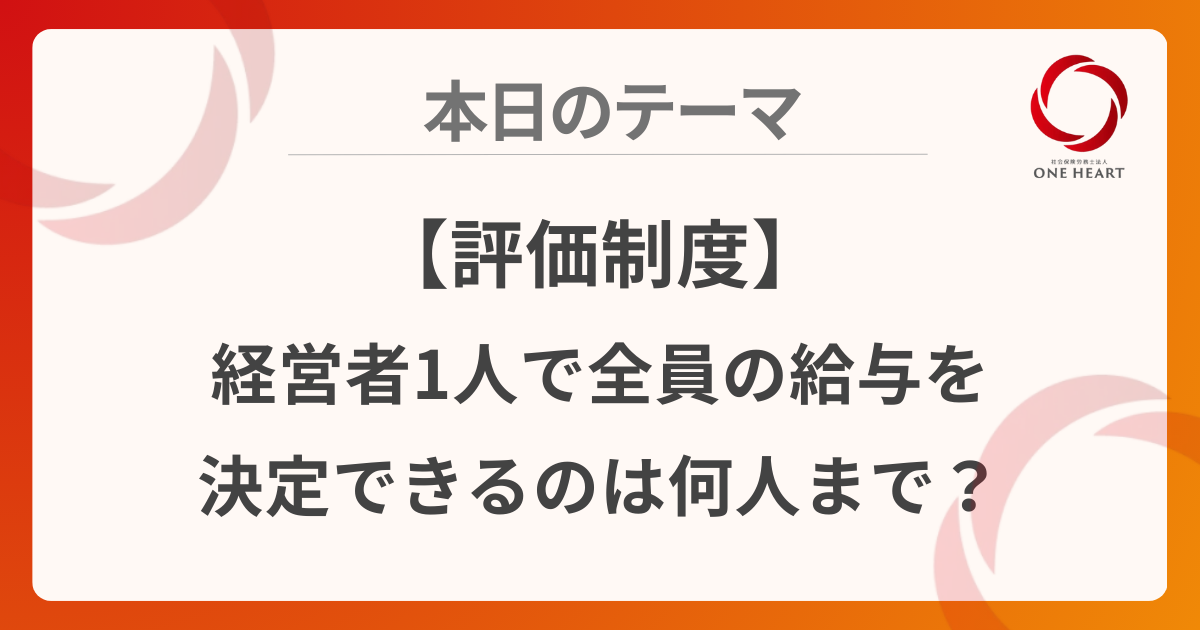
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第35回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
冒頭
「半年に1回の給与改定が大変すぎる…。人数が増えてきて、誰にいくら払うか決めきれない」
そんな経営者の声をよく耳にします。
従業員が20人、30人と増えると、全員の働きぶりを正確に把握して公平に給与を決めるのは至難の業。ある社員の金額を決めると、別の社員とのバランスが気になって最初に戻ってしまう…そんな“堂々巡り”に陥ることもあります。
実はこれ、経営者の能力不足ではなく、会社の成長段階が引き起こす構造的な問題です。そして、その解決策となるのが「人事評価制度」です。
1. なぜ30人を超えると給与決定が難しくなるのか
社員数が増えると大変になる理由は、単に人数や業務量の問題ではありません。
背景には、
- 評価の「ものさし」がないと、多数の社員を適正に評価できない問題
- 一度決めた給与を後から下げることが法律上難しいという問題
があります。
労働契約法では、賃金をはじめとする労働条件を不利益に変更するには労働者の同意が必要で、しかもその同意は、労働者の自由な意思に基づく必要があります。つまり給与は、一度決めると、簡単に下げることができない“不可逆的な約束”なのです。
例えば、ある製造業の社長が「今期は利益が出たから頑張った社員に月給を5万円ずつ上乗せしよう」と判断したとします。翌年、業績が落ち込んだため元に戻そうとしても、「給与が下がるのはおかしい」と社員から反発され、同意を得られずに固定費が膨らんだままになってしまうケースがあります。こうなると、経営の自由度は大きく損なわれてしまいます。
2. 人事評価制度が社員のやる気と納得感を生み出す理由
優れた人事評価制度には大きく2つの目的があります。
2-1. 公正な処遇で給与決定の透明性を高める
客観的な基準で仕事ぶりや能力を評価し、給与・賞与・昇格に反映。経営者の主観に左右されにくく、従業員の納得感が高まります。
例えば、営業部の社員AさんとBさんが同じ売上額を上げていても、Aさんは新規顧客開拓が多く、Bさんは既存顧客対応が中心という違いがあります。評価基準が曖昧だと「なぜ同じ成果なのに評価が違うのか」と不満が出ますが、成果やプロセスも含めて基準化すれば、AさんにもBさんにも納得できる説明が可能です。
2-2. 人材育成を促す評価基準の明確化
会社が「どのような行動や成果を評価するのか」を明文化し、従業員が努力の方向性を定められるようにする。これにより“会社の価値観とズレた頑張り”を防げます。
具体的に、あるIT企業では「深夜まで働く社員よりも、定時内に高い成果を出す社員を評価する」と明言しています。これにより、以前は長時間労働が評価につながると思っていた社員が、効率化や業務改善に力を入れるようになり、組織全体の生産性が向上しました。
ただし、「公正な処遇」という土台がなければ、「成長支援」のためのフィードバックも受け入れてもらえませんことが多いでしょう。
3. 制度導入の目安は「30人の壁」属人的判断から仕組み化へ
私は、従業員が30〜40人に達したら遅くとも制度導入を検討すべきだと考えています。
一人の経営者が直接把握できる人数には限界があり、この人数規模を超えると属人的なマネジメントは通用しなくなります。
例えば、飲食チェーンのオーナーが一つの店舗を運営し、全従業員が20名程度のときは、毎日顔を合わせて話せるため、感覚的な給与判断でも大きな不満は出ません。しかし30人を超え、店舗が2つ以上に増えると、現場を直接見られる機会が減り、評価の根拠があいまいになってトラブルが増える傾向にあります。
「30人の壁」は、組織が“関係性”で動く段階から、“仕組み”で動く段階へ移るサインです。
4. 制度運用で気をつけたい評価エラーと4つの思い込み
制度を作るだけでは十分ではありません。評価を行うのは人であり、その評価者が無意識に陥る心理的な偏り(評価バイアス)が大きな落とし穴になります。
代表例:
- ハロー効果:目立つ特徴に引きずられて全体評価が偏る
- 寛大化傾向:嫌われたくない心理から評価が甘くなる
- 中心化傾向:評価の差をつけず平均に寄せてしまう
- 対比誤差:評価者自身と比較して判断する
具体的に、管理職Cさんが自分の得意分野である営業スキルを重視しすぎた結果、営業成績は平均的でも裏方業務を完璧にこなす社員の評価を低くしてしまった…という事例があります。これでは制度の公平性が損なわれ、社員のモチベーション低下を招きます。
これらを防ぐには、評価者研修を行い、客観性を担保するスキルを磨くことが欠かせません。
5. 評価制度を成功に導く制度設計と評価者教育のポイント
人事評価制度を成功させるには、
- 自社の価値観を評価項目に落とし込む制度設計
- 評価者が正しく運用できるようにする研修
この両方が必要です。どちらか一方では制度は形骸化してしまいます。
まとめ|30人の壁を超えても成長を続けるために
- 経営者一人で給与決定できるのは30人前後まで
- 30人を超えたら属人的マネジメントから制度運用へ移行
- 制度の目的は「公正な処遇」と「人材育成」
- 評価者のバイアス対策として研修が不可欠
人事評価制度は、従業員の納得感を生み、会社の未来を支える投資です。自社の現状と将来を見据えて、導入のタイミングと運用体制を整えていきましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。