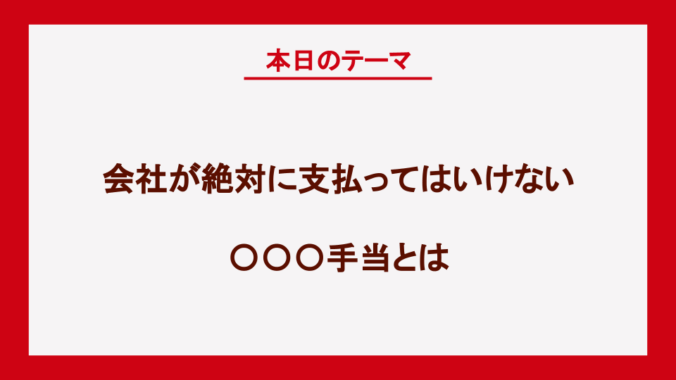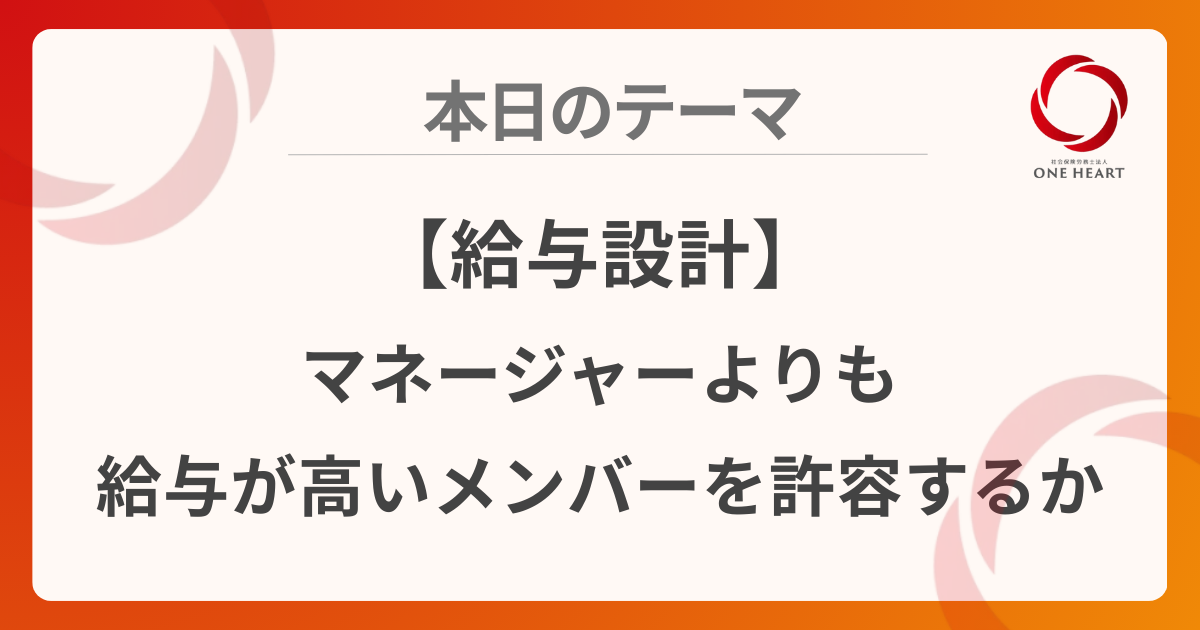
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第31回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
多くの企業が抱える「名プレイヤー、名監督にあらず」のジレンマ
「スキルはあるが、マネジメントには向いていない」。こうした従業員の処遇について、多くの経営者や人事担当者が頭を悩ませています。特に、高い専門性を持つ人材、いわゆる「スペシャリスト」の給与を考える上で、管理職とのバランスは重要な課題となっています。
日本の多くの企業では、依然として「管理職=給与が高い人」という単線的なキャリアパスが主流です。しかし、この制度には大きな弊害が潜んでいます。スポーツの世界で「名プレイヤーが必ずしも名監督になるとは限らない」と言われるように、ビジネスの現場でも、トップ営業担当者が優れた営業部長になれるとは限りません。個人のスキルと、チームをまとめ、部下を育成するマネジメントスキルは全くの別物だからです。実際に、アナウンサーとして非常に高い技術を持っていた方が部長になったものの、組織のマネジメントに苦労し、結果として部下が振り回されてしまったという事例も見受けられます。本人はもちろん、周囲の従業員にとっても望ましくない状況と言えるでしょう。
単線的なキャリアパスがもたらす優秀な人材の流出リスク
管理職になる以外に昇進・昇給の道がない制度は、企業にとって大きなリスクをもたらします。それは、優秀な専門人材の流出です。
特にエンジニアやデザイナー、研究者など、高度な専門性が求められる職種では、「管理職には興味がないが、自らの技術や知識を深め、貢献度に見合った評価を得たい」と考える従業員が少なくありません。そうした人材にとって、マネジメント職への昇進しか選択肢がない状況は、成長の機会を制限されているのと同じです。結果として、「この会社にいても給与は頭打ちだ」と感じた優秀な人材が、より良い評価制度や活躍の場を求めて他社へ転職したり、独立したりするケースは後を絶ちません。
この問題は、一企業だけの課題ではなく、日本全体の構造的な課題として認識されています。政府が推進する「働き方改革実行計画」においても、「単線型の日本のキャリアパスを変え、再チャレンジ可能な社会としていく」ことが重要な目標として掲げられています。年功ではなく能力で評価する人事システムへの転換は、個人の能力を引き出し、企業の競争力を高めるために重要な取り組みなのです。
解決策としての「複線型人事制度」とその社会的背景
こうした課題を解決する有効な手段が、「複線型人事制度」の導入です。これは、従来の管理職を目指す「マネジメントコース」に加え、専門性を追求して組織に貢献する「スペシャリスト(専門職)コース」という、複数のキャリアパスを設ける制度を指します。
この制度を導入することで、従業員は自らの希望や適性に応じてキャリアを選択できるようになります。会社としても、マネジメントが不得手な専門人材を無理に管理職に登用する必要がなくなり、適材適所の人員配置が可能となります。近年、従業員との面談を通じてキャリアの意向を確認し、本人の希望を尊重しながらコースを決定する企業が増えており、既に多くの企業で導入されている制度です。
こうした動きは、国が推進する「多様な正社員」制度とも方向性を同じくしています。これは、職務内容や勤務地、労働時間を限定することで、従業員が多様な働き方を選択できるようにするものです。スペシャリストコースは、まさにこの「職務限定正社員」の一つの形と捉えることができます。専門職としての役割を明確に定義し、その貢献を評価する仕組みを整えることは、現代の企業にとって重要な経営戦略と言えるでしょう。
制度設計の鍵:職務の価値に基づく合理的な処遇
複線型人事制度を導入する上で重要な論点が、「マネージャーよりも給与が高いスペシャリスト」を許容できるかという点です。結論から言えば、これは十分に可能ですし、合理的な制度設計の結果と言えます。
重要なのは、給与を役職の上下ではなく、それぞれの「職務の価値(ジョブバリュー)」に基づいて決定するという考え方です。管理職は、多くの部下をまとめ、組織目標の達成に責任を負う非常に難易度の高い職務であり、その責任に見合った報酬が支払われるべきです。しかし、企業の根幹を支える革新的な技術を開発するエンジニアや、会社のブランド価値を大きく左右するトップデザイナーなど、その人にしかできない専門性によって会社に大きな利益をもたらすスペシャリストも存在します。その職務の価値が、特定の管理職の職務価値を上回るのであれば、給与が逆転することは合理的であると言えます。
この考え方は、「同一労働同一賃金」の原則にも通じます。ハマキョウレックス事件や大阪医科薬科大学事件などの最高裁判例は、正規・非正規といった雇用形態の違いを理由とした不合理な待遇差を認めていません。これらの判例が示すのは、待遇差を設ける場合には、職務内容や責任の範囲、貢献度などに応じた客観的・合理的な説明が必要であるという点です。この法理は、社内の異なるコース間の処遇を設計する上でも、重要な指針となります。
法的観点から見る制度導入の注意点
複線型人事制度、特にスペシャリストコースを設ける際には、法的な注意点を十分に理解しておく必要があります。専門職としてのキャリアを保障することは、裏を返せば、会社側の配置転換の権限に制約がかかることを意味するからです。
従業員を特定の職務に限定して採用した場合、それは法的に「職務限定の合意」があったと解釈される可能性があります。過去の裁判例(東武スポーツ事件)では、キャディとして採用された従業員を会社が一方的に他職種へ配置転換することは許されないと判断されました。つまり、スペシャリストとして採用した人材を、本人の同意なく全く異なる職務へ異動させることは、原則としてできないのです。これは人材の定着に寄与する一方、組織の硬直化を招くリスクもはらんでおり、導入には慎重な検討が求められます。
ただし、長年同じ職務に従事したからといって、直ちに職務が限定されたと見なされるわけではない点も判例(日産自動車村山工場事件)は示しており、あくまで個別の雇用契約の内容が重視されます。
もう一つの重要な注意点は、コース間の異動、特に管理職から専門職への「降格」です。最近の裁判例(東京地裁令和5年6月9日判決)では、会社が管理職を非管理職(スペシャリスト)へ降格させ、賃金を一方的に引き下げた事案で、従業員の同意がないことを理由にその措置を無効と判断しました。この判例は、専門職コースを能力不足の管理職の「受け皿」として安易に利用することの危険性を示唆しています。制度の公正性と信頼性を保つためにも、コース間の異動ルールは明確に定め、本人の適切な同意を得るプロセスを構築しなければなりません。
まとめ
「名プレイヤー、名監督にあらず」という言葉が示す通り、従来の単線的な昇進・昇給モデルは、現代の多様な人材を活かす上で限界を迎えています。優秀な専門人材の能力を引き出し、彼らの流出を防ぐためには、管理職コースと専門職コースを併設する「複線型人事制度」の導入が有効な戦略となります。
その核心は、役職ではなく「職務の価値」に基づいて処遇を決定することにあり、その結果として専門職の給与が管理職を上回ることも、合理的な判断として適切であると言えます。ただし、その導入と運用にあたっては、職務限定に伴う配置転換の制約や、コース間異動のルールなど、法的な論点を慎重に検討する必要があります。
こうした複雑な人事制度の設計・導入は、人事労務の専門的な知見が必要となります。社会保険労務士法人ONE HEARTでは、各企業の理念や事業戦略に合致した、実効性と法的妥当性を両立する人事・賃金制度の構築を支援しております。自社の人事制度の見直しをご検討の際は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。貴社の持続的な成長を支える人材戦略をご提案いたします。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。