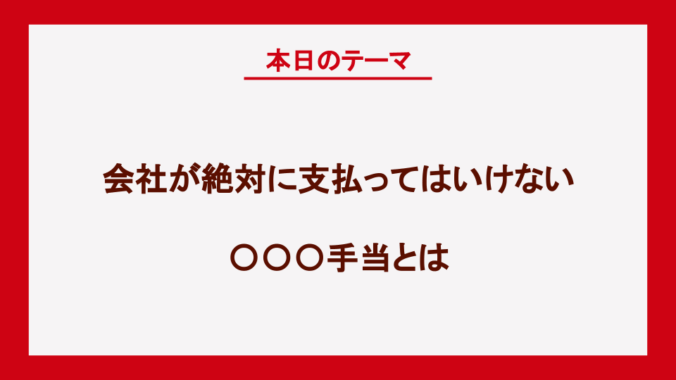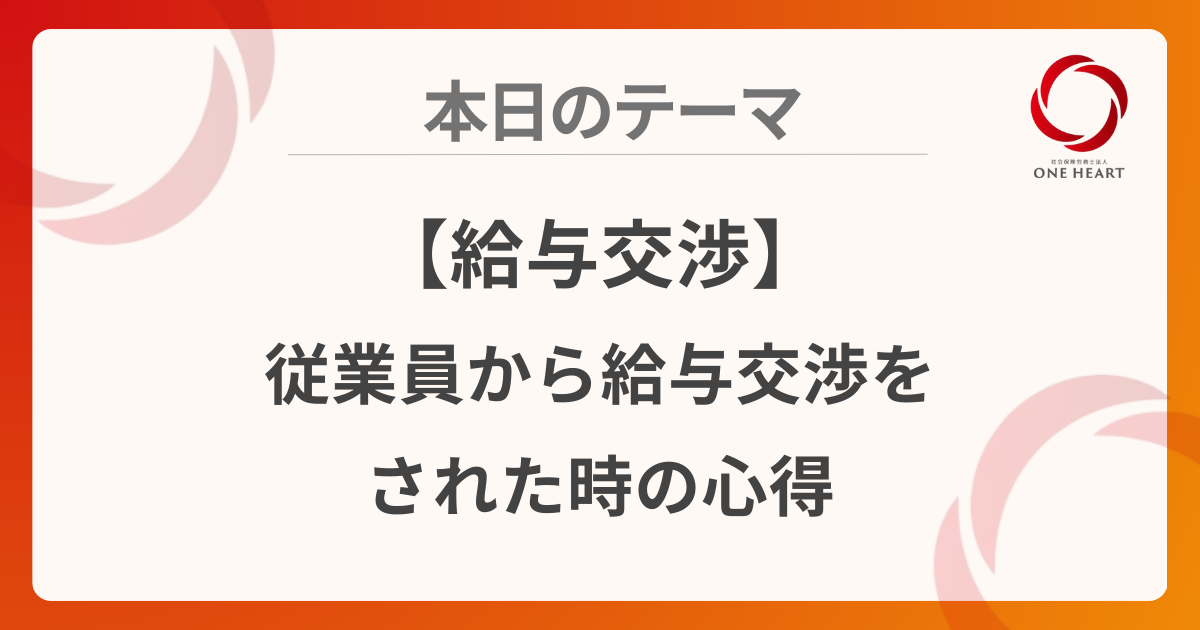
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第40回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
はじめに:給与交渉は組織の健全性を映す「鏡」
「部長、お時間をいただけますでしょうか。実は、給与について相談があるのですが…」
こんな申し出を受けたとき、経営者や人事担当者の方はどのような気持ちになるでしょうか。「面倒なことになった」「断るべきか、応じるべきか」といった戸惑いを感じる方も多いかもしれません。
しかし、従業員からの給与交渉は、決して「厄介事」として片付けるべきものではありません。むしろ、それは貴社の人事評価制度や賃金制度が適切に機能しているかを知る貴重な機会なのです。
従業員が直接給与について申し出るということは、現在の評価や処遇に何らかの疑問や不満を抱いているということ。つまり、平常時のコミュニケーションや評価制度に改善の余地があることを示す「危険信号」と捉えることが大切です。
給与交渉の背景を理解する:2つの動機パターンを見極める
従業員から給与交渉を持ちかけられた際、まず取るべき行動は結論を急ぐことではありません。その背景にある動機をじっくりと聞き取ることが重要です。
評価への不満が根底にあるケース
「私の働きや成果が正当に評価されていない」という思いから生じる交渉です。
- 「同僚と比べて自分の方が貢献しているのに待遇が変わらない」
- 「重要なプロジェクトを成功させたのに昇給がない」
- 「会社は自分の価値を理解してくれていない」
このような感情が背景にある場合、単に金額の問題ではなく、評価制度そのものへの不信が根深くある可能性があります。
個人的事情による経済的必要性
仕事の評価とは直接関係なく、生活環境の変化によるものです。
- 家族構成の変化(結婚、出産、親の介護など)
- 住宅ローンや教育費などの固定費増加
- 配偶者の収入減少による家計への影響
この場合、要求の背景にあるのは貢献度への不満ではなく、純粋に生活上の経済的必要性です。
この2つのパターンを混同して対応すると、問題の本質を見誤ってしまいます。まずは先入観を持たず、従業員の話に真摯に耳を傾けることが不可欠です。
交渉への対応判断基準:戦略的な判断と円満な着地点
「代替可能な人材」への対応
会社にとってその従業員が退職しても構わないと考えており、交渉に応じることが他の従業員との公平性を欠くと判断される場合は、丁重に、しかし毅然とした態度で要求をお断りすべきです。
適切な断り方の例:
「ご相談いただいた件について検討いたしましたが、当社の給与制度や評価基準に照らし合わせると、現時点での昇給は難しいという結論に至りました。」
個人的な感情ではなく、組織としてのルールに基づいた決定であることを明確に示します。
「代替が難しい人材」への対応
会社にとって重要な人材から交渉があった場合は、真摯に話し合いのテーブルにつくことが安全です。ただし、この話し合いを「会社のお金を奪い合う」といった対立構造にしてはいけません。
建設的なアプローチの例:
「あなたにこの新しい業務を達成していただければ、会社としてご希望の給与を支払うことが可能になります。この目標にチャレンジしていただけませんか?」
将来の貢献と報酬を結びつける提案により、双方にとって前向きな着地点を見出すことができます。
即決は厳禁:冷静な判断時間の確保
いずれのケースにおいても、その場で結論を出すことは避けるべきです。たとえ昇給を認める心づもりがあったとしても、一度持ち帰り、冷静に検討する時間を持つことが重要です。
根本的解決策:公平な評価・給与制度の構築
個別の給与交渉が頻発する根本的な原因は、多くの場合、社内に明確で公平な人事評価制度や給与制度が存在しないことにあります。
効果的な人事評価制度の要素
以下のプロセスが重要です。
- 期初面談:評価者と被評価者が具体的な業務目標を設定
- 期中フォロー:進捗状況の確認と必要に応じた軌道修正
- 期末評価:達成度の客観的評価とフィードバック
- 複層的評価:直属上司だけでなく、上位役職者も関与する体制
場当たり的対応と体系的アプローチの違い
場当たり的な給与決定では、従業員からの不満が表明されてから初めて対応を考えるケースが多く、管理者の主観や属人的判断に頼りがちです。評価基準が不透明で、結果的に不公平感を生みやすいです。
一方、体系的なアプローチでは、定期的な評価サイクルの中で客観的基準や目標達成度に基づいて判断します。評価基準を全従業員に公開することで透明性が高く、公平性と一貫性を担保できます。
まとめ:予防的な組織づくりが最善の対策
従業員からの給与交渉は、組織が抱える問題を可視化してくれる貴重な機会です。重要なのは、目先の要求への対応だけでなく、なぜそのような交渉が起きたのかという根本原因に目を向け、再発を防ぐための仕組みを構築することです。
今すべき3つのアクション
- まず傾聴する
交渉を組織の健全性を測るデータと捉え、従業員の真の動機を深掘りする - 戦略的に対応する
その場での即決を避け、会社の状況と従業員の重要度を冷静に判断し、将来を見据えた着地点を探る - 制度を構築する
場当たり的な対応から脱却し、公平で透明性の高い人事評価・賃金制度を設計・導入する
給与交渉への適切な対応や、その根本原因となる人事評価制度の構築には、専門的な知識と経験が必要です。社会保険労務士法人ONE HEARTでは、各企業の実情に合わせた公平で戦略的な人事・賃金制度の設計から導入、運用までを一貫してサポートしております。
従業員の誰もが納得感を持ち、意欲的に働ける組織づくりに向けて、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。専門家の視点から、貴社に最適な解決策をご提案いたします。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。