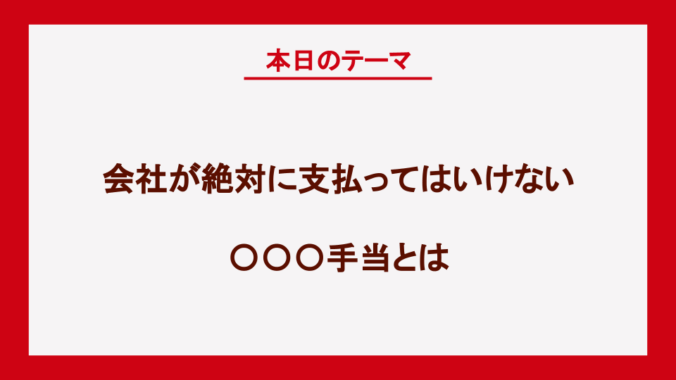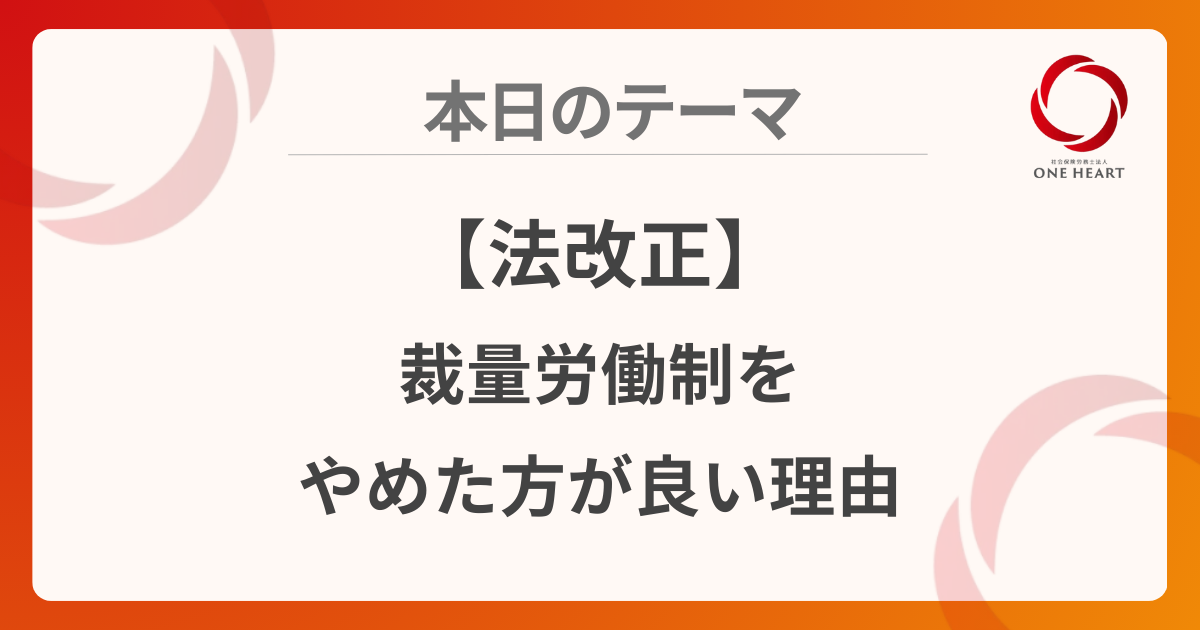
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第104回、第105回の配信をもとに書かれた記事です。
【法改正】裁量労働制をやめた方が良い5つの理由(前編)
【法改正】裁量労働制をやめた方が良い5つの理由(後編)
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
裁量労働制という働き方を耳にしたことはありますか?これは、労働者と使用者の間で労働時間を決めると、実際に働いた時間に関係なく、決めた時間労働したとみなす制度です。一見便利な制度ですが、ここだけを切り取って制度を導入してしまうと、管理運用面で大変な思いをしてしまいます。今回のコラムでは、よく使用されているけど誤解の多い専門業務型裁量労働制について、導入をおすすめしない理由を解説いたします!
専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制とは、業務の遂行方法を労働者が決定するため、手段や時間配分について、経営者が具体的に指示をすることが困難な仕事に限り、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度です。例えば、労働時間を8時間と決めた場合は、実際の労働時間が何時間であっても8時間とみなされることが最大の特徴であり、10時間働こうが7時間働こうが、一律8時間働いたものとして扱われます。
この業務の種類は決まっており、コピーライターや弁護士など、高度な専門性が求められる職種が対象とされます。
よくある間違いとして、「みなし時間を設定すれば、無限に働かせることができる」という考え方があります。残業代を払いたくないと考える経営者の方や、研究に没頭したいから労働時間を気にしたくない労働者の方がこの考え方をしているのかもしれません。
この制度は、「仕事がはかどった日は7時間、時間が押してしまった日は9時間労働していた。平均すると大体8時間なので、労働みなし時間は8時間にしよう。」という考えが前提にあります。制度設計の際にこの考えを念頭に置かないと、経営者の意図に合わず、想定していない長時間労働が発生してしまい、未払い残業代の支払いを命じられたり、労働時間の管理が不十分になってしまったりするので、注意が必要です。
適用範囲の不明確さ
私が専門業務型裁量労働制の導入をおすすめしていない理由はいくつかあります。1つ目は、適用範囲が不明確なところです。
例えば、テレビ局で働いてるディレクターは、音声や映像、照明、美術などのスタッフに指示をして、撮影を進める番組制作現場の責任者を指しており、自身で仕事の方針や時間配分を決定している仕事のため、専門業務型裁量労働制を適用できると言われています。一方、アシスタントディレクターはディレクターの指示に従ってアシスタントを行っているだけなので、適用できないとされるのが一般的です。
それでは、会社の中でディレクターとアシスタントディレクターの中間の役職ができた場合は、専門業務型裁量労働制を適用できるのでしょうか。この場合は、業務内容を精査してみないとわかりません。このように、自社の役職に当てはめると、制度を適用できるかどうか明確になっていない「グレーゾーン」が存在してしまうことがあるのです。
その他にも、役職名と実態が合っていないと、後から「私は細かい指示を受けて働いているので、本来は制度の適用ができないはずだ」と主張され、未払い残業代が発生する可能性もあります。適用できるか不明確な役職があると、このようなリスクが考えられるので、導入はおすすめしておりません。
同意書の作成
導入をおすすめしない理由の2つ目は、同意書の作成が必要であることです。2024年4月から労働基準法が改正されて、専門業務型裁量労働制を適用するには労働者本人の同意が必須になりました。
この同意が必須になったことによって問題になるのは、本人が同意を撤回したら、どのような対応が必要になるのかということです。撤回の手続きは事前に定めておく必要があり、撤回後の処遇等は、あらかじめ決議しておくことが望ましいとされています。
厚生労働省が作成している協定例では、「本人同意が行われる前の部署における同職種の労働者に適用される人事制度及び賃金制度を基準に決定するものとする。」と記載があります。推測するに、専門業務型裁量労働制のコースと、普通のコースの2種類ある会社が、同意を撤回した時には、普通のコースに戻ることを想定している内容でしょう。
しかし、そもそも複数のコースが用意されていない中小企業も多いはずです。もし労働者から「同意を撤回しても給料はそのまま、残業代も1分単位で払ってほしい」と言われれば、人件費が膨大になってしまう恐れが高まります。労働者の希望によって同意の撤回ができてしまう以上、処遇等の整備をきちんと行ってからでないと制度の導入は難しいでしょう。
運用面の難しさ
理由の3つ目は、運用面の難しさです。「1日8時間労働と見なされるから、タイムカードさえ切れば1分だけ出社しても8時間働いたとみなされる」という極端な行動を取る従業員が出る可能性もあります。
もちろん、完全に働いていない場合は懲戒処分も検討されますが、一部労働している場合は処分する根拠が難しく、会社側の管理が追いつかなくなってしまいます。つまり、「放任」や「曖昧」な労務管理になりやすく、トラブル発生時の対応も複雑化するリスクがあります。
労使協定書作成のハードル
そして、4つめは労使協定書の作成です。専門業務型裁量労働制を正しく導入するには、労働者代表を民主的に選ぶ選挙を行うなど、厳格な手続きを踏んだうえで労使協定書を作成する必要があります。しかし、多くの中小企業・スタートアップでは「過半数代表者が選挙で選ばれていない」など不備が散見されます。
「実際は専門業務型裁量労働制の要件を満たさないまま運用していた」という例も多く、あとで未払い賃金が発生したり、労使トラブルに発展することもあります。こうしたリスクを考えると、やはり導入のハードルは高く、慎重に検討していかなくてはなりません。
まとめ
専門業務型裁量労働制は「業務範囲の不透明さ」「同意撤回への対応」「労使協定書の作成」などクリアすべき課題が多く存在します。業務実態と合わないまま導入すれば、未払い残業代などのトラブルに直面するリスクは大きいでしょう。
私は10年以上社会保険労務士として会社を見させていただいていますが、細かい制度設計までできてる会社はほとんどありません。管理面の煩雑さからも、専門業務型裁量労働制の導入は安易に行わない方が良いでしょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
【法改正】裁量労働制をやめた方が良い5つの理由(前編)
【法改正】裁量労働制をやめた方が良い5つの理由(後編)
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。