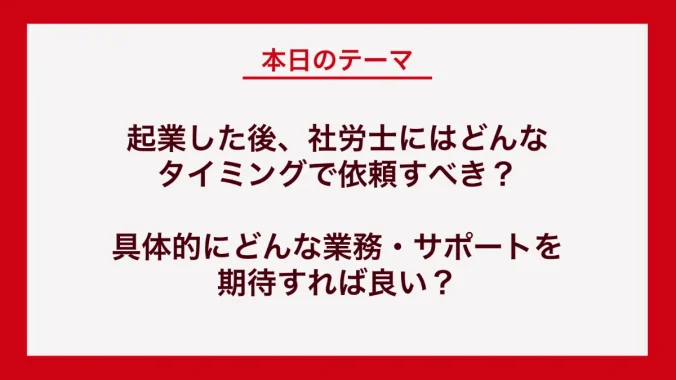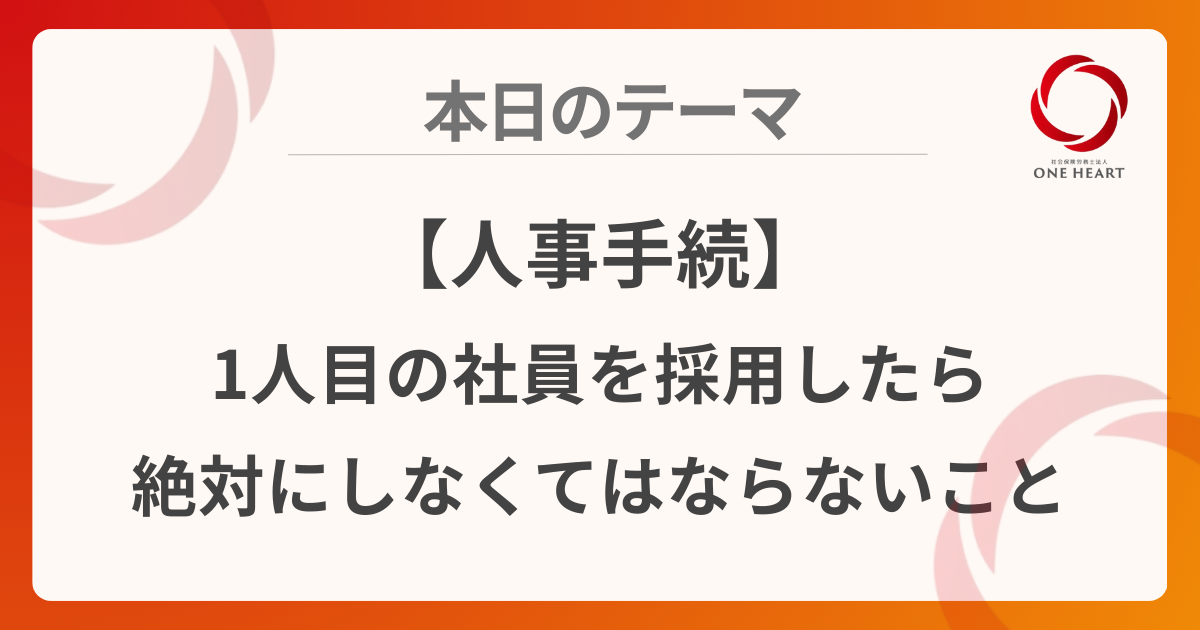
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第81回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
事業が軌道に乗って、従業員を雇うことになった際、会社が行わないといけない手続きはどのくらいあるのでしょうか。手続きが漏れてしまうと、従業員との間の信頼関係がなくなり、離職に繋がってしまう可能性があります。今回は、初めて社員を採用したときに必ず行わなくてはならない手続きを解説いたします!
入社前に行うこと
採用を決めた際に、会社が1番初めに行うことは、内定通知書の発行です。書類の発行義務はありませんが、内定辞退を防ぐ意味でも発行することをおすすめします。
今回のテーマである、1人目の入社を悩まれている会社ですと、募集枠が1、 2名と少ない傾向にあります。そのような中で、内定を辞退されてしまうと、採用がすべてやり直しになってしまいます。
そのため、可能であれば内定通知書を直接手渡して、どのような期待があって採用した人材かということを、熱量高く話しましょう。会社の一員としての自覚を持ってもらうことで、内定辞退される可能性を減らしていくのです。
入社前後に必要な書類
続いて、入社前後で必要な書類を見ていきましょう。入社前に受け取っておくべき書類として、入社誓約書があります。入社誓約書は、内定者の入社する意思を確認するために提出してもらうものです。法的な効果はありませんが、内定通知書同様、内定辞退のリスクを軽減するためにも提出してもらいましょう。
次に、入社後に必要な書類として、身元保証書があります。身元保証書には、本人の身元を確認することはもちろん、本人と連絡が取れなくなった緊急時の連絡先を入手する目的もあります。本人が企業に損失を与えた際の請求先として設定しておくことも可能なので、何かあった時のために受領しておいた方が良いでしょう。
そして、雇用契約書です。労働基準法上、労働時間や賃金等の労働条件を明示した、労働条件通知書を発行しなければならない義務があります。必要なのはあくまで通知書ですので、会社が労働者の方に通知すれば問題ありませんが、一方的な通知だと、聞いていません、見ていません、と言われてしまう可能性があります。そのため、雇用契約書という形で、会社と本人の双方の合意が確認できるような文書を作ることをおすすめしています。
また、「労働条件通知書と雇用契約書、それぞれ1つずつ作らなくてはいけないのですか」という問い合わせを受けたことがありますが、労働条件通知書兼雇用契約書と形で、1枚の書類にまとめることが可能です。どこの会社も合理的に進めたいと思っているので、労働条件通知書と雇用契約書を一体型にして締結しているケースが多い印象です。
その他にも、健康診断の実施が必要です。安全衛生法では、以下の従業員を雇い入れるときは、入社時に健康診断を行わなくてはならないと定められています。
・常時使用する労働者
・パート・アルバイトのうち、次の1~3までのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者
1. 雇用期間の定めのない者
2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)使用される予定の者
3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)引き続き使用されている者
(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6ヶ月以上健康診断を行わない場合、50万円以下の罰金を支払わなくてはならない可能性があります。
入社後の手続き
会社として初めて雇用する1人目の従業員の場合、まず、労災保険に加入しなくてはなりません。労災保険は人ごとに入るものではなく、会社が加入するものですので、2人目以降に関しては、基本的に自動で適用されていきます。支店を出したり、新しく事業所を作ったりする場合は、また労災保険の加入手続きが必要になるケースもありますので、所轄労働基準監督署や社会保険労務士に確認し、正しい手続きを行いましょう。
次に、雇用保険の加入です。週20時間以上働く人は、雇用保険に加入させなくてはなりません。これを怠ってしまうと、退職時に失業手当をもらうことができません。大きく揉める原因になりますので、必ず行うようにしてください。
<雇用保険の加入基準>
次の1及び2のいずれにも該当するときは、雇用保険の手続きが必要です。
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
そして、社会保険手続きです。こちらも怠ってしまうと、従業員が病気になり、病院に行こうとした際に、健康保険証がないという事態に陥ります。健康保険証がないと医療費の10割を負担しなければならないので、従業員に迷惑をかけないためにも、きちんと手続きを行いましょう。
社内手続き
続いては、社内手続きです。先ほどは労務視点での法的な観点をお伝えしましたが、法的なハードルをクリアしたから入社手続きが終了するわけではなく、その会社独自に使用しているものの用意も行わなくてはなりません。
例えば、製造業であれば、制服やヘルメット、工具を発注するといった作業が必要です。事務職であれば、アカウントの発行等が該当します。当社の場合、勤怠管理システムであるキングオブタイムのアカウント発行や、 給与明細を見るためにマネーフォワードクラウド給与のアカウント発行を行います。他にも、Slack、チャットワーク、Notion等のアカウント発行、メールアドレスの設定など、会社ごとに使用しているツールを設定しておく必要があります。
また、1人目の入社の時に行った手続きは、記録しておくことをおすすめします。これを行っておくと、2人目以降の入社の際に非常に役に立ちます。
当社では、Notionというツールの中に、入社時に行うことリストを作成しています。スタッフは、私を含めて5人体制ですが、採用するたびに、項目は増えています。1人目の時に手続きを行っていたけど、記録し忘れてしまっているなど、きちんとリストを作っていないと抜け漏れが起きてしまうので、気を付けて作成しましょう。
入社後の待遇は同一に
細かいことですが、 後々言われないように気を付けたいのは、入社後の待遇を同一にすることです。例えば、Aさんの入社時には歓迎会があったけれども、Bさんの入社時には何もなかった。これは、Bさんにしてみると、自分が期待されていないと思い、意欲が下がってしまう可能性があります。そのため、歓迎会やランチ会なども含めて、全員を同じような形で受け入れましょう。この点は抜け落ちてしまいがちなので、頭に入れておくとよいでしょう。
まとめ
今回は1人目の入社手続きについて、お伝えしました。手続きが多いので、とても人を採用することができない、と思ってしまうかもしれませんが、リストを作成して網羅する、不安なところは専門家に依頼するなど、自分に合ったやり方で、まず、1人目の手続きを行いましょう。
初めての採用では、法的な手続きだけでなく、社員を気持ちよく迎え入れるための準備も重要です。長期的な関係を築くためにも、これらの手順を丁寧に踏み、スムーズな受け入れを行いましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。