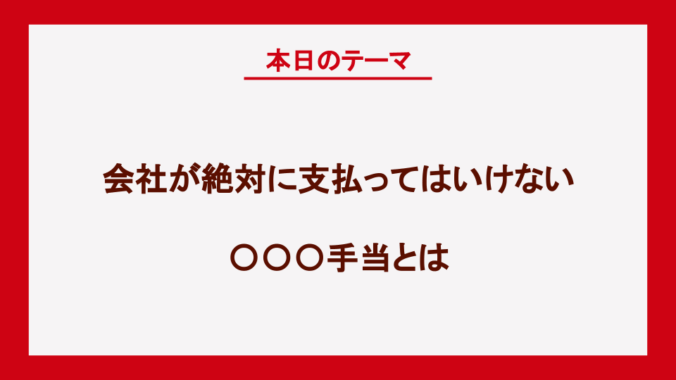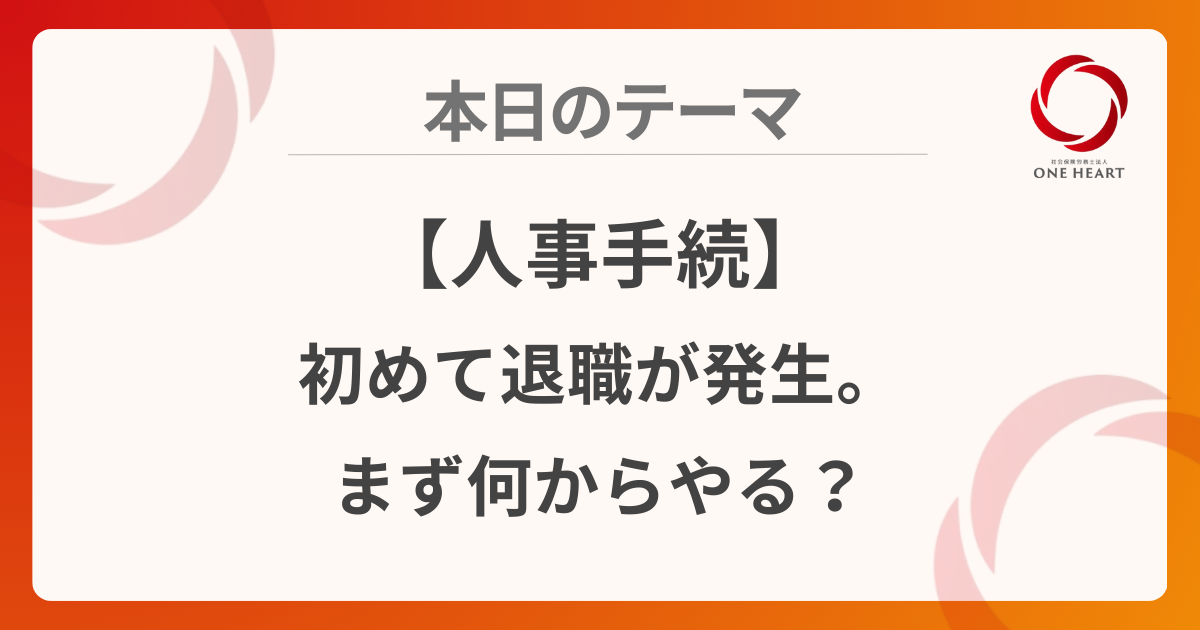
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第82回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
今回のテーマは、1人目の退職。初めての退職者が出ると、経営者からするとかなり堪えてしまいますよね。実際に行う退職手続きのうち、法律上行わなくてはならないことは、そこまで多くありません。今回は、退職に必要な手続きを、時系列で解説していきます!
退職届及び誓約書の受理
従業員から退職の報告を受けた際、まず行うことは真意を確かめることです。まれに退職を迷っているケースもあります。引き留めに賛否がありますが、退職理由を聞いて、退職の意思が固ければ、退職希望日を聞きます。
次にやることは退職届を受理することです。自己都合退職を前提としていますが、自ら辞めたという証拠がないと、後から「私は会社から辞めさせられた」と言われてしまう可能性があります。法律上、必ず提出しないといけないものではありませんが、「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、本人に退職届を書いてもらい、会社で保管しましょう。
また、退職届と一緒に、誓約書も書いてもらいましょう。一般的には、機密保持、競業避止の文言が入った誓約書をご提出いただくケースが多いです。会社の情報を持ち出さないという確認を文書で行うことができますので、誓約書は提出していただくようにしましょう。
引継ぎ計画の作成と管理
退職届を受理したら、次に行うことは、業務の引継ぎ計画を作成することです。退職者が出てしまうと、その方が行っていた業務の引継ぎを行わなくてはなりません。そのため、引継ぎスケジュールを作成することが必要です。
退職者の性格によって、最後まで引継ぎに協力的な方もいれば、退職が確定した途端、手を抜く方もいらっしゃいます。会社の管理としては、手を抜く人がいるかもしれないという前提で動いた方が安心ですので、「じゃあ、引継ぎをしておいてね。よろしく」と後任者に丸投げするのではなく、 上長や責任者の方が、引継ぎ計画をきちんと管理して作成しましょう。もしくは、退職者が引継ぎ計画を作成したのであれば、それが適正なものなのかどうか管理したり、引継ぐ側が引継ぎ計画を作成するのであれば、それが実現可能なものなのかを確認したりすることが、必要になります。
また、引継ぎ計画では、有給の消化がポイントとなります。有給の申請が上がってきていないと、会社としては、在籍期間の最終日まで実際に出社して引継ぎをしてもらえると考えてしまいがちですが、本人にそんなつもりはなく、最後の1ヶ月は有給を取るつもりだった、ということがよくあります。有給を使う権利は非常に強く、残りの労働日が20日しかなく、20日の有給がある時に、20日全部使わせてくださいと言われたら、会社は基本的にそれを認めなくてはなりません。
場合によっては交渉して、退職金を支給する代わりに出社してもらうことも、不可能ではありません。しかし、本来、有給は買い取ることができません。このようなことにならないためにも、有給の消化予定をしっかり確認したうえで、引継ぎ計画を作成しましょう。
会社備品等の返却
引継ぎ計画を作成し、その通りに引継ぎを行った最終出勤日には、備品等の貸与品の返却を行っていただきます。パソコンを持ったまま退職してしまったり、会社の制服を返却せずに退職してしまったりする方は珍しくありません。備品の返却漏れがないか、リストを作成して確認を行いましょう。
備品のほかにも、受け取っておかなくてはならないものとして、健康保険証があります。退職によって健康保険の資格がなくなると、保険証を使用することはできません。新しい保険証は、退職者が転職した場合は転職先、扶養に入る場合は扶養者の会社、個人事業を営む場合は国民健康保険で、手続きを行った後に発行されます。そのため、現在使用している保険証は回収し、日本年金機構に返却しましょう。
退職者への書類交付
続いて、退職者へ交付する書類を見ていきましょう。まずは、源泉徴収票です。転職する際は転職先に提出を、その後就職をしなかった際は自身で確定申告をする際に必要なので、必ず本人に交付しましょう。
次に、離職票です。これは、雇用保険の失業給付を受ける際に必要な書類です。本人が希望しなければ発行不要ですが、忘れた頃に発行を依頼されるよりも、原則、発行して渡す流れを作っておくとよいでしょう。
その他にも、年金手帳など、個人のものを会社が預かっている場合は返却が必要になるので、忘れないように注意しましょう。
退職後に必要な手続き
従業員が退職した後に行う手続きとして、社会保険及び雇用保険の資格喪失届、住民税の異動届の提出があります。順番に確認していきましょう。
まずは、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出です。従業員が退職した場合、事実発生から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出が必要になります。回収した健康保険証と一緒に提出を行いましょう。
次に、雇用保険では、雇用保険被保険者資格喪失届と、給付額等の決定に必要な離職証明書の提出が必要です。 従業員が離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければなりません。
そして、税金関係では、給与所得者異動届出書の提出が必要です。これは、住民税の納付者や納付方法を変更するための書類で、従業員が退職した日の翌月10日までに、退職者が居住する区市町村に提出する必要があります。なお、住民税の徴収方法は、退職した月によって異なります。
6月1日から12月31日までに退職した場合は、普通徴収に切り替えることになり、退職者が直接市区町村に納付します。退職者から申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収します。
1月1日から4月30日までに退職した場合は、残りの税額を、給与や退職金等が超える場合には、退職者の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して徴収します。なお、5月退職の場合も、特別徴収として、給与から徴収します。
その他社内手続き
最後に、必要な社内手続きを確認します。まずは、アカウント関係です。いつまでも削除していないと、会社の機密情報が退職者から閲覧し放題になってしまうので、退職者が使用していたアカウントは、削除するもしくは、使用不能にする必要性があります。また、システムによっては、個人のアカウントがなく、パスワードで入るものもありますから、退職者がでたら必ずパスワード変更をするという仕組みを作っておきましょう。
そして、退職金の支給です。退職金制度がある会社は、規定に基づいて支給する金額を計算し、支給しなくてはなりません。その際は、必要に応じて税務署に提出できるように、退職所得の受給に関する申告書を退職者に記入してもらい、会社で保管しておきましょう。退職金を支給した場合は、退職金にかかる源泉徴収票の発行も必要になりますので、忘れないように注意しましょう。
まとめ
何をすべきかわからない状態だと、初めての退職者が出たことによって気が滅入ってしまうのに加えて、事務手続きに不安になってしまいます。退職は必ず起こるものなので、To Doリストを作成し、漏れることがないようにしっかり対応していきましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。