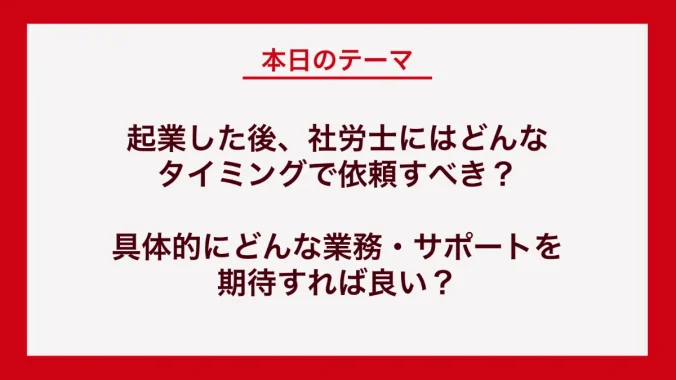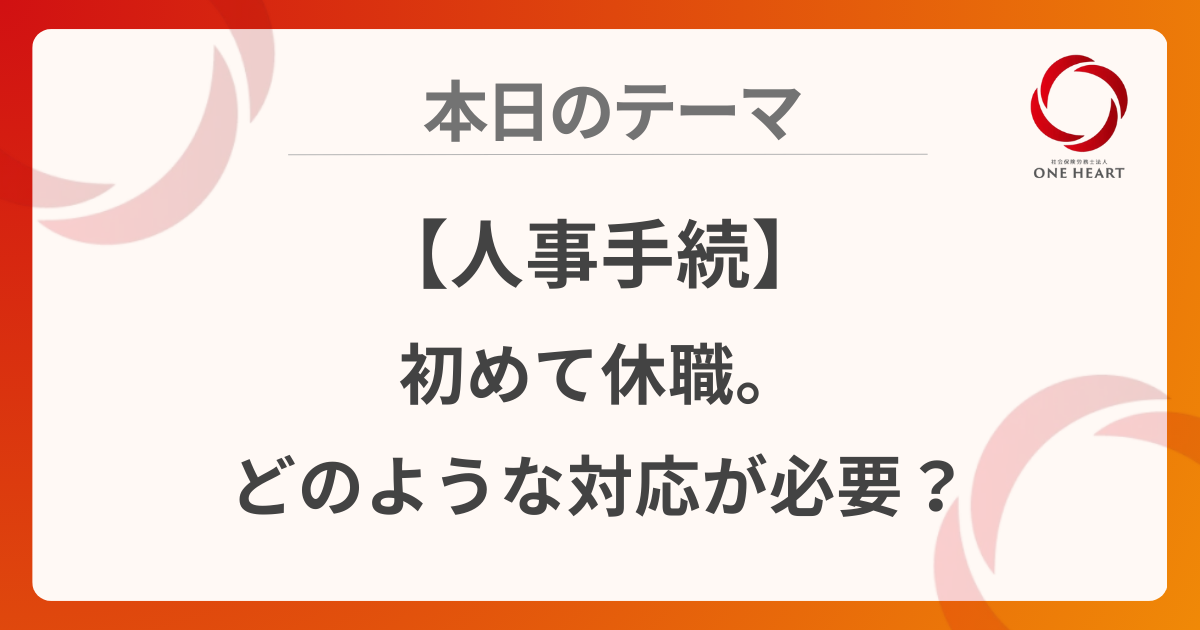
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第83回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
会社を経営していると、従業員から「少し休ませてもらえませんか。」と相談を受けるケースがあると思います。初めて休職の手続きを行う時、会社としてどのような対応が必要でしょうか。今回は、従業員から休職の相談を受けた時に行う適切な対応についてお伝えいたします!
休職制度の重要性
休職制度とは、従業員が傷病の療養や特定の理由で、一定期間会社を休むことができる制度です。この制度は、必ず設けなくてはならないものではありませんが、従業員が安心して働く環境を提供するために、多くの会社が就業規則に規定しています。
休職制度がない会社で、私傷病など従業員本人の都合で働くことができない場合、その従業員は最終的に解雇されてしまいます。厳しいようにも聞こえますが、会社と従業員は、お給料を支払う代わりに、働いてもらうという契約を交わしているため、どちらか一方が履行されてない状態になると、それは当然に解約できてしまうのです。
しかし、契約通り働けなかったらすぐに解雇されてしまうと、従業員は安心して働くことができません。そのため、多くの会社は、解雇を一定期間待ってもらえる休業制度を設けています。これを休職制度といいます。この期間は会社によって異なり、短いところで3か月、長いと2年ぐらい休業できるところもあります。
就業規則がある会社の中には、テンプレートにあったからという理由で、休職制度を設けている会社もあります。そのような休職制度は自社にあっていないこともあります。例えば、零細企業が大企業と同じような休職期間も長く休職中も給与を支給するような休職制度をもうけていると会社にとって大きな負担になる可能性があります。自社の休職制度がどのようになっているか、必ず確認しておきましょう。
休職対応の具体的手続き
それでは、具体的な手続きについて確認していきます。従業員から休職の相談を受けたら、まず、その理由と期間を確認しましょう。休職制度の適用を考えるにあたり、休職の理由が何で、どのぐらい休まなくてはならないのかを、会社として把握しておく必要があるためです。
一番確実なのは、医師の書いた診断書を提出してもらうことです。そうすることによって、病気が完治するまでの期間を把握できるため、復職のスケジュールを組みやすくなります。
休職理由と期間の確認が終わったら、就業規則に則って手続きを行います。「1ヶ月間欠勤が続いたら休職を適用する」と記載がある場合は、1ヶ月間欠勤が続いたら休職制度を適用しましょう。
また、休職に入る際は、休職辞令という書類を発行することをおすすめします。口頭で休職を伝えてしまうと、後に言った、言わないで揉める可能性があります。いつからいつまで休職なのか、休職期間中の給与はどうなるのか、社会保険料の自己負担分をどのように精算していくのかなどを記載した休職辞令を発行し、認識の違いがなくなるようにしておきましょう。
トラブル防止のために必要なこと
休職手続きは従業員とトラブルになりやすい事項の1つです。トラブルを防ぐためには、就業規則の通りに手続きを進めることが大切です。
よくある間違いは「1ヶ月間欠勤が続いたら休職を適用する」というルールが就業規則にあるにもかかわらず、1個月未満しか欠勤していないのに休職させてしまうというものです。このような手続き違反となるので、復職の際に会社と労働者で復職の可否について見解が分かれた場合、会社が不利な状況になる可能性があります。
6か月という休職期間を設定した従業員がおり、それが就業規則に記載のある期間の上限だったとします。その間に復職できないと退職になってしまいますが、いざ退職となると、「やっぱり辞めたくない」とか、「もう少しで治る」という話が出てくることが多くあります。
従業員が復職したいと思っている一方で、会社がこれ以上待つことができない状況の時、休職に入る時の手順が就業規則通りでないと、手順がおかしいから、私はまだこの会社に居続けることができるという主張をされてしまう可能性があります。そのため、就業規則に記載してある手順は必ず守りましょう。
会社に合った制度設計を
従業員が安心して労働できる環境を守るための休業制度ですが、過度な規定を盛り込む必要はありません。例えば、犯罪の疑いがあり、一定期間拘留されている間も休職を認める起訴休職や、地方議員や国会議員などの公職に就いたから休職させる公職休職です。
どちらも素晴らしい規定だとは思いますが、中小企業で設けてしまうと、突然、「地方議員になったので休職させてください。2年間休みます」と言われても、その間の人員をどう手配するか困ってしまいます。起訴休職の場合も、いつ復職できるのかわからないので、同様ですね。スタートアップ企業やこれから伸び盛りの会社であれば、病気休職を規定する程度で十分だと考えます。
まとめ
休職は制度がある以上、申し出があった場合に認めなくてはなりません。手厚い規定を盛り込む必要なないので、従業員の心身の不調に対応できるように規定を見直しておくと安心です。
最近はメンタル不調で休職を行うケースも増加しています。休職の相談は突然やってきますので、相談を受けた際は慌てず、就業規則の通りに手続きを進めていきましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。