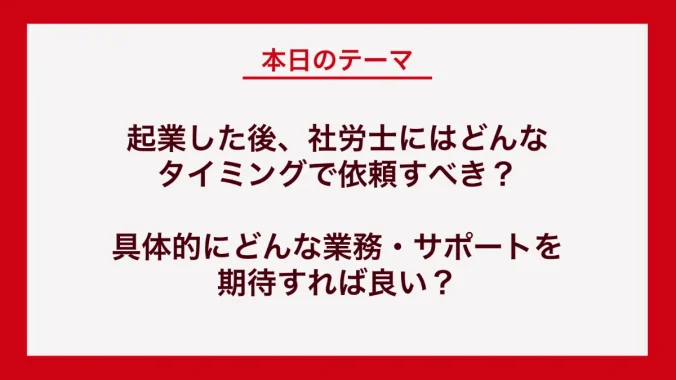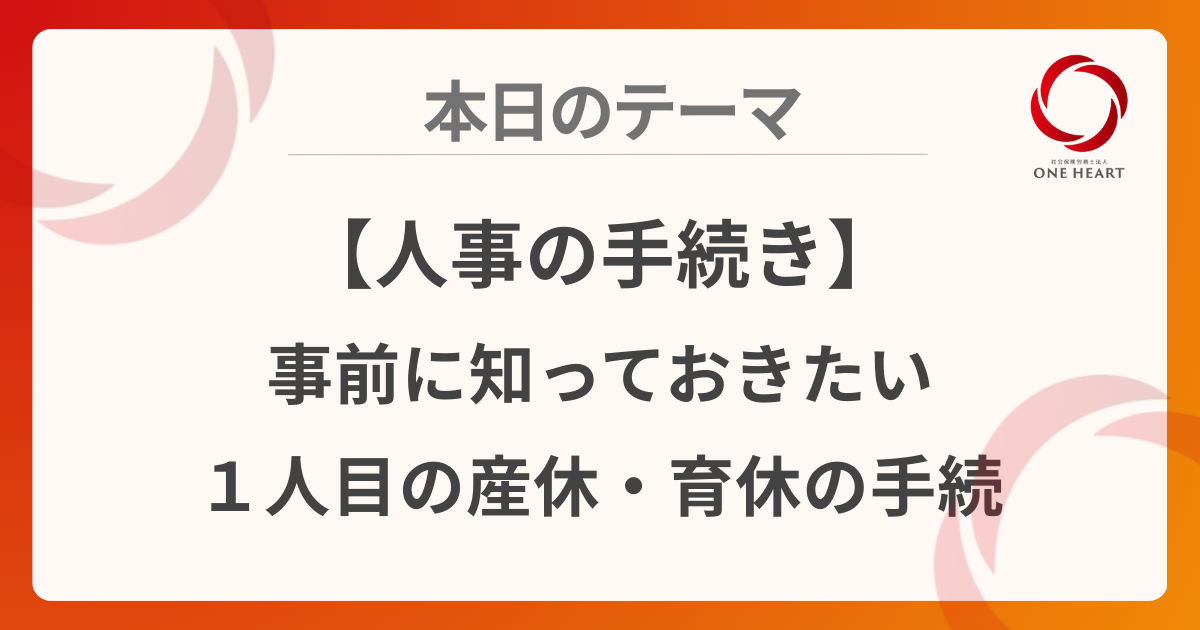
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第86回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
従業員が妊娠し、産休・育休を取得したいという相談があった場合、どのような対応が適切でしょうか。就業規則の整備が追い付いていないがゆえに、「当社には産休・育休の制度がありません」などと回答してしまうと、会社の評判を落としてしまいかねません。今回は、労務担当者や経営者が知っておくべき産休・育休の手続きについて解説します!
産休・育休は取得の申し出を断ってはいけない
産休・育休の申し出が従業員からあった場合、原則として会社はそれを断ることはできません。言葉の定義を確認しますと、産休(産前・産後休業)とは、労働基準法で定められている休業で、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、出産の翌日から8週間(ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合を除く)まで、請求すれば取得することができる制度です。
また、育休(育児休業)は、育児・介護休業法によって定められている休業で、労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまで(一定の場合は、子が1歳6か月又は2歳に達するまで)の間、取得することができる制度です。
法律で定められていますので、従業員には休みを取得する権利があります。間違えて申し出を断ってしまうと、マタニティハラスメントととらえられてしまう可能性もありますので、注意しましょう。
スケジュールの確認
従業員から妊娠の報告を受けた際は、まずはお祝いの言葉を伝えましょう。妊娠をしたという事実はとてもおめでたいことですからね。そのあと、出産予定日と産休・育休の取得期間を確認します。
産休は出産予定日の6週間前から入ることが多いですが、つわりがひどいと、その前から病気休職という形でお休みに入るケースもあります。他にも、慣れ親しんだ環境で出産をしたいという意向で、早い段階から実家に帰る方もいらっしゃいますので、どのタイミングから休業を開始するか、従業員と会社の認識を早めに合わせておくと良いでしょう。
そして、難しいのが復帰のタイミングです。育休は、子供が1歳になるまで取得するのが一般的ですが、保育園の待機児童問題などにより、2歳まで延長されるケースもあります。家庭によっては1歳になるよりも早く復帰するケースもありますので、従業員の希望を聞きつつ、復帰目安時期を整理していきましょう。
代替人員の検討
産休・育休取得に伴い、業務の引き継ぎや代替要員の確保が必要となるケースがあります。1年から2年ほど欠員してしまいますので、妊娠の報告を受けたら、休業期間を考慮し、採用や配置転換などの対応を検討しましょう。場合によっては、派遣社員やパートでの採用もあるかと思いますが、産休・育休に入る従業員の業務内容を検討し、残った人に仕事が集中してしまわないように、適切な人材の確保に努めることが大切です。
会社が行う手続き
続いて、会社が行う手続きを確認していきましょう。まず、産休の際には、産前産後休業取得者申出書の提出を行います。こちらは従業員が産休を取得したとき(産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)に提出することによって、産休中の健康保険・厚生年金の保険料納付が、従業員と会社の両方とも免除されます。
そして、育休に入る際には、4種類の書類が必要になります。1つ目は、出産手当金支給申請書です。被保険者が出産のため会社を休み、会社から報酬を受けられないときは、出産手当金が支給されます。出産手当金が受けられる期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。
2つ目は、育児休業等取得者申出書です。この申出書は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内に提出する必要があり、提出を行うと、健康保険・厚生年金の保険料は、従業員と会社両方の負担が免除されます。
3つ目は、休業開始時賃金月額証明書です。こちらは次に紹介する育児休業給付金を受給する際に必要な書類です。休業を開始する前の給与の支払額を確認するための書類で、ハローワークに提出する必要があります。
4つ目は、育児休業給付受給資格確認票および、(初回)育児休業給付金支給申請書です。育児休業給付金を受けるためには、会社が受給資格確認を行う必要があります。受給資格があれば、育児休業給付受給資格確認通知書と育児休業給付金支給申請書が交付されるので、育児休業給付受給資格確認通知書は従業員に渡し、育児休業給付金支給申請書はハローワークに提出しましょう。
なお、出産の事実に伴い、出産育児一時金支給申請書を提出すると、48.8万円〜50万円支給されます。こちらの書類は基本的に従業員が提出するため、会社としての作業は必要ありません。出産した子供を従業員が扶養する場合は、会社が健康保険被扶養者異動届を提出する必要があります。
復帰した際には、養育期間標準報酬月額特例申出書や育児休業等終了時報酬月額変更届が提出をすることをおすすめします。
産休・育休に関する手続きは、数が多く、複雑なものも多いです。労務担当者や経営者の方のストレスを減らすために、専門家である社労士に依頼することをおすすめします。
男性の育休取得
育児休業でお伝えしておきたいのが、男性の育休取得についてです。近年、男性の育休取得は増加傾向にありますが、女性の育休と比べて取得時期が予測しにくいという特徴があります。というのも、配偶者の方が妊娠してるという報告を会社に行うとは限らないからです。法律上、1ヵ月前に申し出があれば育休を取得させなければなりませんが、急な申し出に対応することは難しい場合も多いでしょう。
最近では法改正が行われ、「労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等」が新設されました。育休・産後パパ育休の取得意向を確認するために面談を実施することや、家庭環境による勤務地等の希望確認が義務付けられているため、会社側としても対応することが必要になります。研修などを通して、育休取得を検討している場合は早めに会社に申し出るよう促すなどのルールを設定しておくとよいでしょう。
まとめ
産休・育休は、誰もが取得する可能性のある制度です。そのため、会社は休業を取得する可能性がある人を適切に把握して、その方とスケジュールの共通認識を持つことが重要です。従業員とコミュニケーションを密にとり、安心して制度を利用してもらえるように心がけましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。