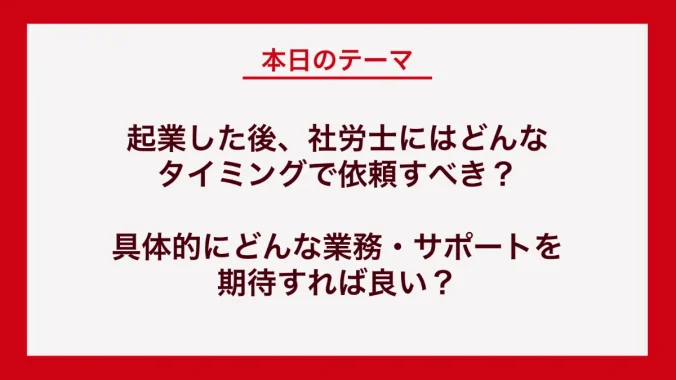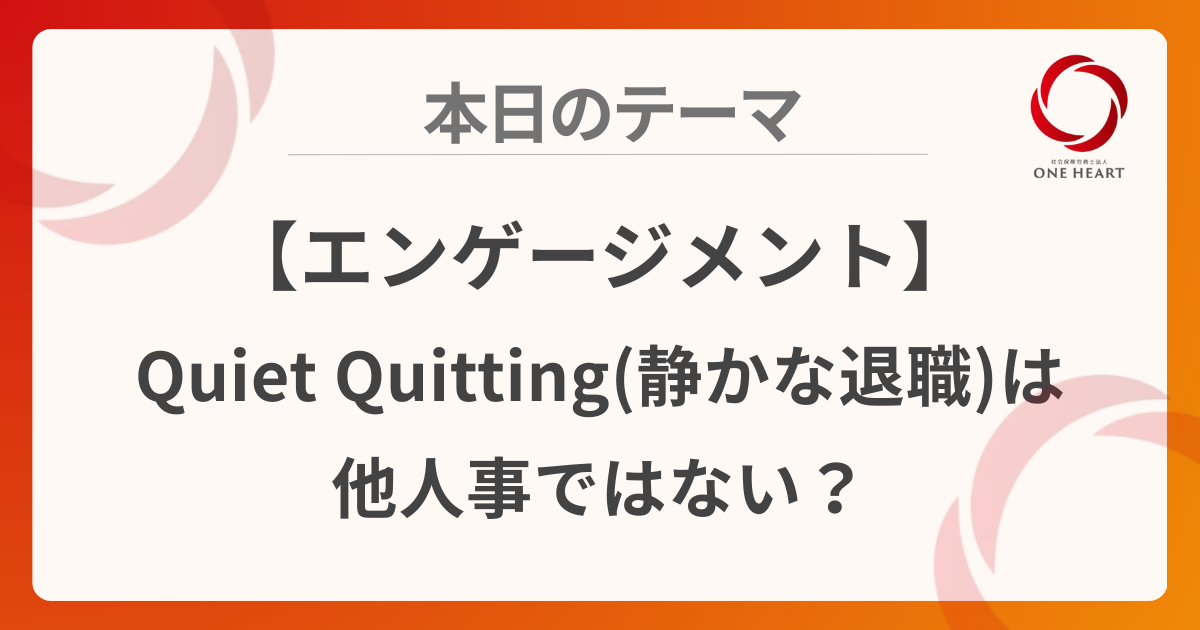
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第38回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
2022年にアメリカを中心としてQuiet Quittingという働き方が話題になりました。多様な働き方が求められる昨今、日本でも同じような現象は見られるのでしょうか?今回は、Quiet Quittingの働き方と対策、放っておいた場合にどんな影響があるのか、お伝えします!
Quiet Quittingとは
Quiet Quittingは、日本語に直訳すると「Quiet =静か」、「Quitting=辞める」のため、静かな退職とも言われています。実際に会社を辞めるわけではなく、会社には在籍しているけれども、必要最低限の業務しか行わない働き方を指します。
これは2022年に英語圏を中心としてSNSで流行した言葉で、仕事にかける労力を必要最低限にして、プライベートの時間を大切にすることを提言したものです。「仕事=人生」という考え方を見直すことは、多くの若者からの支持を集め、社会現象となりました。
コロナ禍で急増
今までも似たような考え方はありましたが、コロナウイルスの影響で働き方が変化したことによって、急激にこの考え方が浸透していったと考えられます。コロナ禍で在宅勤務が増加した結果、職場の仲間と会う頻度や出社する回数が減少し、仲間意識や会社への帰属意識が薄れていってしまったのです。
同じ空間で仕事をしていれば、隣の人が忙しそうだからと手伝ったり、優秀な人に憧れて、自分もそうなれるように努力したりするかもしれません。しかし、同僚と実際に会わない状態で仕事をしていると、他人の仕事を気にすることなく、自分の仕事だけを最低限やっておけば良い、というマインドが働いてしまいます。
以前は窓際族と呼ばれている、出世コースを外れたおじさんがこのようになってしまうことが多かったのですが、Quiet QuittingはZ世代まで広がっています。若い世代も仕事に熱意を持たない状態で就業していることが、今までと異なるところです。
日本のエンゲージメント
会社に対する従業員の帰属意識などを示すエンゲージメントですが、世界的に見ても、日本の順位は極めて低いとされています。2017年と少し前のデータですが、「熱意あふれる社員」の割合が6%という結果となっており、調査した139カ国中132位と最下位クラスでした。
過労死という言葉が海外にも浸透しているくらい有名なため、日本のエンゲージメントが低いのは意外な結果だと考える人も多いかもしれません。しかし、それだけ会社と自分の関係性をドライに考える人が増加してきたということでしょう。
元々低いエンゲージメントがコロナ禍を経てさらに低くなったというのが、今の日本の現状です。エンゲージメントを高くするために、会社はどのような取り組みをすればよいのでしょうか。
エンゲージメントを向上させるには
社員のエンゲージメントを高めるために会社が行うべき対策は、2つあります。1つ目は、目標と評価基準をはっきりさせることです。あなたにはこういう役割を期待していて、その対価としてお給料を払っているということを、きちんと説明しましょう。その役割と評価基準に納得したうえで働いてもらうと、自分が会社に対してどのように貢献しているかわかるため、エンゲージメントの向上につながる可能性があります。
2つ目は、コミュニケーションに投資することです。今までの環境だったら同じ空間にいるので、ちょっと教えてもらうとか、雑談をすることが気軽にできました。しかし、リモートでは文章だけのやり取りになるため、意識しないとコミュニケーションをとることが難しくなってしまいます。
私も以前、「吉田先生はいつ忙しいかわからない」と言われた経験があります。忙しい時期がわからないと気軽に相談もできないため、あらかじめ面談の時間を決めておき、時間を確保しておくというのは有効な方法だと思います。カレンダーアプリで予定や締め切りを共有しておくのも効果的ですね。
対策をしない場合の影響
皆さんにお伝えしておきたいのは、エンゲージメントを高めるために、意識してコミュニケーションの時間を取ることが大切ということです。この問題を放っておくと次のような影響が出てしまう可能性があります。
リモートで作業を行っていると、誰が何をしているのかよくわからない、という状況が前提あります。しかし、リモート期間が長期にわたると、この仕事にそんなに時間はかからないよな、と上手くサボっている人がわかるようになってきます。その時に、あの人も仕事していないなら、私もちょっと手を抜こうかなと考える人が出てきてしまいます。
高い目標を持って仕事をしている優秀な社員がいたとしても、同僚の仕事ぶりを見ていたら、この会社では頑張っても無駄だと、退職してしまう可能性が非常に高いです。その結果、Quiet Quitting状態の社員ばかりになってしまうというリスクがあります。
さらに、新しくやる気がある状態で入ってきた社員も、それを見れば同じように同質化してしまい、新たなぶら下がり社員を生んでしまいます。そのため、対策をきちんと行った上で、会社運営を行っていくことがとても重要になります。
まとめ
Quiet Quittingが流行した背景には、コロナ禍で定着した在宅勤務という働き方改革によって、会社への帰属意識が低下したり、仕事に熱意を持った社員が減少したりしたことがあります。
プライベートの時間を大切にすることももちろん必要ですが、せっかく1日8時間という時間を労働しているのであれば、仕事時間も充実できるよう、やりがいを感じることや、同僚とのコミュニケーションを取ることができる環境を、経営者と従業員が力を合わせて作っていきたいですね。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。