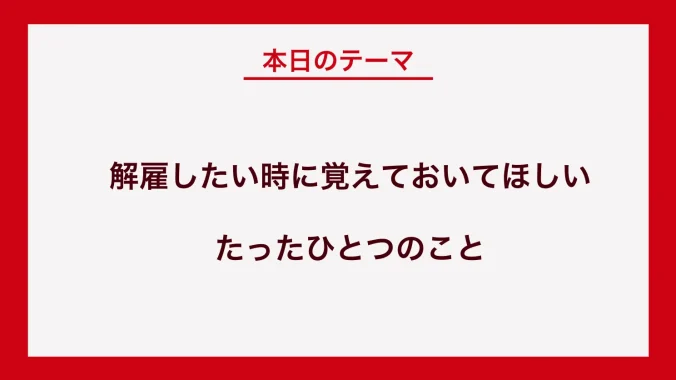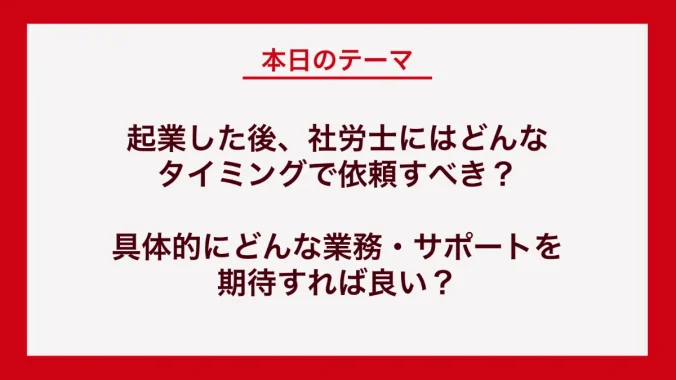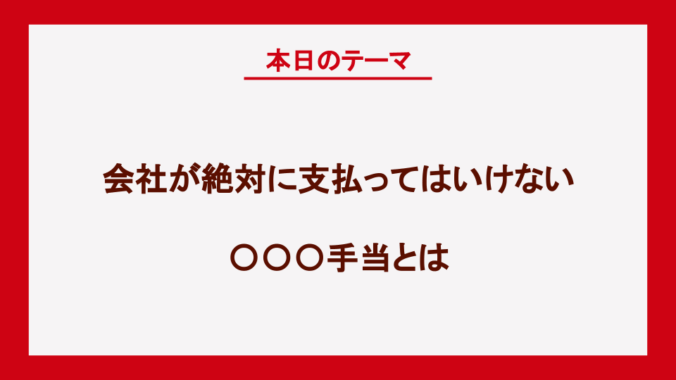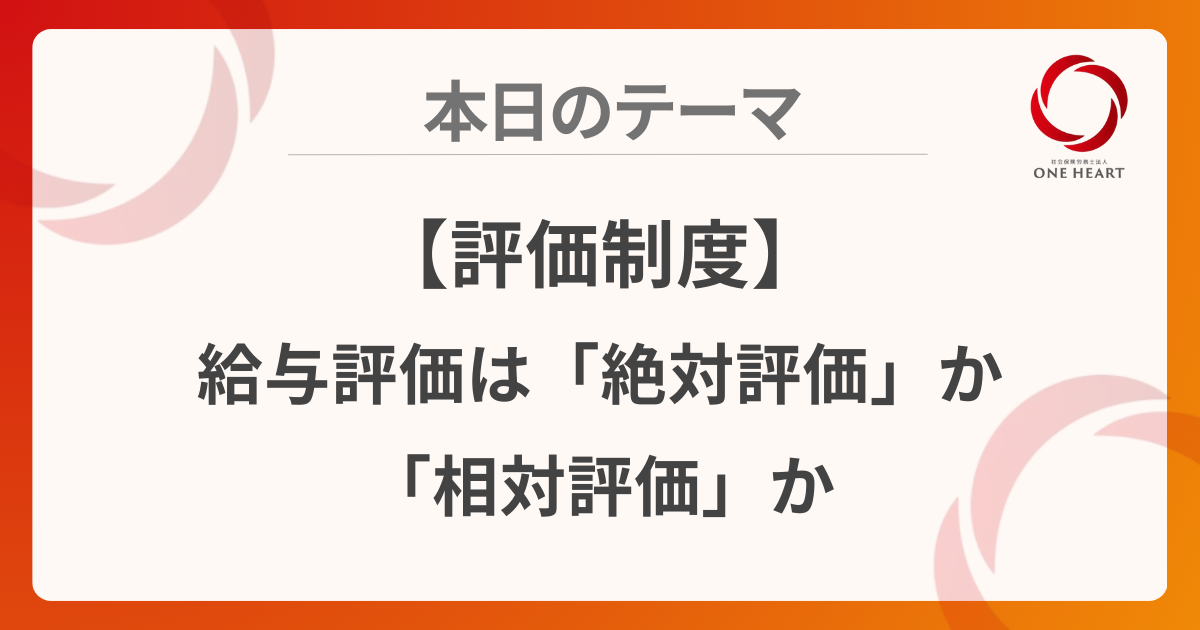
このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第34回の配信をもとに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!
皆さんの会社では、人事評価を行う際に、絶対評価と相対評価のどちらを使用していますか?評価方法の使い方を間違えると、従業員から評価に納得がいかないという不満の声が上がってしまうかもしれません。今回のコラムでは、絶対評価と相対評価の違いと、おすすめの使い方について解説していきます!
絶対評価と相対評価の違い
人事評価で使用されている絶対評価と相対評価ですが、この2つには大きな違いがあります。まず、絶対評価ですが、こちらはあらかじめ決めた基準に則って評価をする方法を指します。テストで例えるなら、100点満点中80点以上はA、60点以上80点未満はB、60点未満はCという基準に則って評価が行われます。自分の取った点数によって評価が決まるので、他の人の影響を受けないことが特徴です。
一方で相対評価は、ある一定の集団の中で、個人の能力を評価する方法を指します。例えば、テストを受けたうちの上位30%はA、中間層40%はB、下位30%はCと評価する方法です。点数で評価を行うわけではなく、全体の中のどこに自分が位置しているかによって評価が決まります。
評価基準が異なるため、同じ80点を取ったとしても、絶対評価ではA、相対評価ではBになってしまうなど、絶対評価と相対評価で評価が異なることがあるのです。
おすすめする評価方法は絶対評価
先ほど挙げた特徴を踏まえて、人事評価を行う際、私は絶対評価を使用することをおすすめします。なぜなら、評価対象者の行動結果だけを見て評価することができるからです。
相対評価を使用していると、評価対象者よりも頑張った人がいた場合、評価対象者の評価が低くなる可能性があります。全社を挙げて取り組んだ新商品の販促に貢献したにも関わらず、他の方の売上の方が高かったので、いつもより販売数は多いけれども今回はC評価、といったことにもなりかねません。そうすると、評価対象者の仕事に対する意欲は下がってしまうことでしょう。
絶対評価を採用していると、その心配はありません。評価対象者の販売数が評価基準に対してどの程度達成されているかによって評価が決まるため、評価対象者の実績が直接評価に反映されることになります。
実績が評価に反映されることは、従業員のモチベーション向上や、やりがいを得ることに繋がってきます。反対に、頑張ったにも関わらず悪い評価がついてしまった場合は、会社が成果を評価してくれないとして、転職してしまうことも考えられます。最悪の事態を防ぐためにも、人事評価は絶対評価で行うことをおすすめします。
評価者の基準の目線合わせ
絶対評価を行う際に、気を付けないといけないことがあります。それは、評価者の基準を合わせておくことです。優しい上司と厳しい上司がいた場合、各々の基準で評価を行ってしまうと、良い評価と悪い評価の人数が極端になってしまうなどして、評価が成立しません。何を行ったらこの評価になるという基準を社内で事前に決定しておき、評価者はその基準に基づいて評価を行うことが重要です。
相対評価の使いどころ
先程説明した例だと、相対評価に良い面がないように思えますが、相対評価にもメリットがあります。それは、会社の資金を管理しやすいところです。会社では、どのくらいの金額を給与にかけることができるという、給与原資が決まっています。相対評価を採用していると、支給総額が決まっているので、評価によって総支給額が増減することはありません。
その他にも、競争を促進したい時に有用です。相対評価は集団の中で評価が行われるため、その集団の中で上位に入るために、従業員同士が切磋琢磨し合います。そうすると、個々の能力が向上する効果も見込まれるので、会社全体のレベルが上がっていくでしょう。
評価方法の使い分け
絶対評価と相対評価はそれぞれにメリットとデメリットがあるため、この2つを使い分けることも効果的です。例えば、人事評価は相対評価を使用し、賞与支給は絶対評価を使用する方法です。
成果が全く報酬に反映されないとモチベーションが低下してしまいますが、賞与査定が絶対評価であれば、人事評価が相対評価だったとしても、評価されなかったという実感が薄れるでしょう。賞与だけを絶対評価にしても、給与総額にそこまで大きな影響を与えることは少ないので、うまく使い分けを行うことができれば、それぞれの評価方法のいいとこ取りをすることができます。
まとめ
絶対評価と相対評価は、どちらにも利点があります。従業員の離職が多くなっている近年では、評価対象者だけの実績で判断できる絶対評価をおすすめしていますが、給与総額が予定よりも増加してしまうリスクがあります。従業員のモチベーション維持か、資金繰りの平準化か、会社経営を行う上で重視していることを決め、それを解決できる評価制度を採用するようにしましょう。
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。