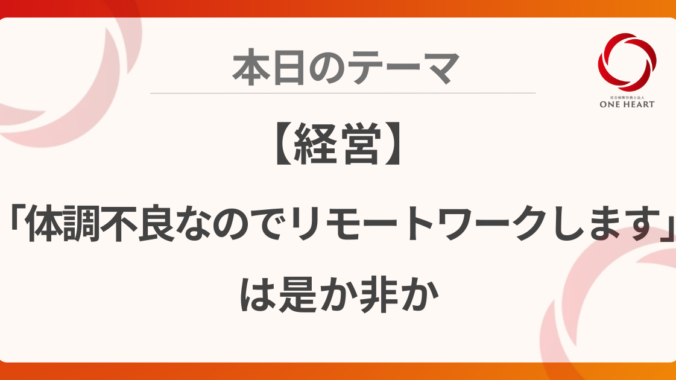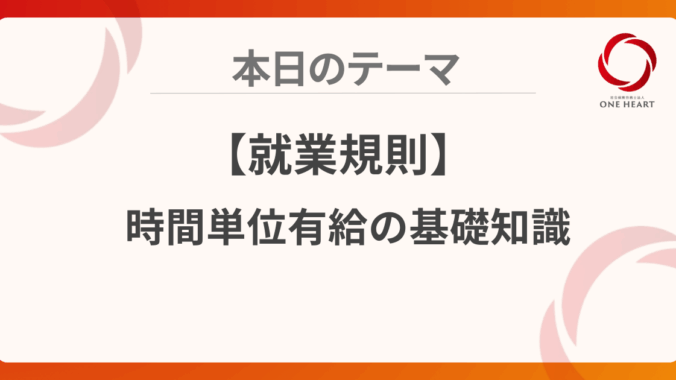このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第2回の配信をも とに書かれた記事です。
Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

会社を設立したとき、いきなり社労士に業務を依頼する方は少ないですよね。税理士などと比べると、社労士には「いつ、何を頼るべきかが見えにくい」という話もよく聞きます。
今回はそんな疑問にお答えするべく、「失敗しない社労士への依頼タイミング」についてお伝えします。
そもそも社労士のサービスとは?
社労士の主なサービスは、労務相談、社会保険の手続きの代行、給与計算の代行、就業規則の作成などを行うことです。社会保険手続きの「面倒くさい」や労務トラブルの「こまった…」を解決するサポートをします。
社会保険労務士法人ONE HEARTでは、スタートアップ・中小企業様に向けて、一般的な社労士サービスのほかオペレーション設計や組織計画など、伴走型サポートを提供しています。

具体的には、勤怠管理を行うKING OF TIMEや、労務手続き・情報管理をオンラインで管理することができるSmartHRなどのITツール導入を支援することによって、効率的な労務管理サポートを行います。そのほか、多くのお客様を支援してきた実績や知見をもとに、目先の問題解決だけでなく、組織の状況に合わせた労務相談・アドバイザリー業務を行っております。

社労士と契約するタイミングは「5人」と「10人」の節目!

社労士との契約を最初に検討するタイミングは、「5人目の従業員が入社するタイミング」です。
なぜなら一人の上司に対する部下の最適人数は5名から10名程度と言われているためです。スタッフが5名以上になると徐々に一人の社長では目が行き届かない部分が発生します。顕在化していなくても、徐々に労務トラブルのリスクが高まっているのです。
さらに、10人以上になると就業規則の作成と届出が必要になります。会社の実態にそぐわないテンプレのような就業規則を作成してしまうと、その後大きな問題に発展してしまう可能性があります。そのため、10人に達する前後で社労士と顧問契約を結び、自社の業務や就業環境について十分に理解した専門家からアドバイスをもらうことが重要です。
【社労士の上手な付き合い方①】正確・スピーディな業務代行により、経営者やスタッフは本来の業務に集中できる!
社労士に業務を委託するメリットは、人材に関する悩みを専門家に任せることによって、本来の業務に集中できることです。
社会保険の手続きや就業規則の作成など、慣れていない人は一から調べなくてはならず時間がかかるだけでなく、間違ってしまうリスクもあります。行政官庁に出向く必要のある手続きだと、より多くの無駄な時間・作業に追われてしまうことになります。そこを労務のプロである社労士に依頼すれば、法律的に問題のない環境づくりができ、さらに社長は本来の業務に集中できるようになるわけです。
また「法律に則った働く環境」を整備することは、労働者にとって働きやすい環境を整えることにつながり、結果優秀な人材が集まりやすくなります。
余談ですが、私が代表を務める社会保険労務士法人ONEHEARTでは、上記のような手続き業務に加えてSmartHR、マネーフォワードなどのITツールの導入支援も取り扱っているのも特徴です。こうしたツールをうまく活用することで、会社経営者の時間創出・スタッフにとって働きやすい環境整備に貢献します。

【社労士の上手な付き合い方②】経営者にとって信頼できる相談相手が社労士!
ここまで記事を読んでいただいたみなさまに知っていただきたいのは、社労士を「ただの作業者」として扱うのは、もったいない!ということです。
どうしても、労務手続きや給与計算といった「事務屋」の側面が強く映ってしまいがちですが、社労士は経営者にとって信頼できる相談相手になるのです。
経営者は大きく二つの悩みを持っています。一つは「おカネの悩み」。そして、もう一つは「ヒトの悩み」です。従業員が増えると、経営者は採用、教育、トラブルなど数多く悩みを抱えます。
トラブルの例を挙げてみましょう。「会社は従業員に残業代を支払っていたが、実はその計算方法が間違っていた」という問題があったとします。そこに労働基準監督署の調査が入り、そのような不適切な処理が指摘され、その事実が社内の従業員間で広まってしまうと、会社の信用はなくなります。そうすると優秀な人が辞職してしまったり、退職者が増えてしまうというリスクに繋がってしまうのです。
こういったトラブルを未然に防ぐには、適切な就業規則や給与制度の設計が不可欠です。社長の性格や会社のカルチャーをよく理解してもらった信頼できる社労士と、二人三脚で制度設計を進めるとベストです。

社労士との顧問契約を遅らせることで発生するリスクとは
冒頭で、4人以下の事務所ならば契約はしなくても良いとお話ししました。しかし、早めに社労士に仕事を依頼することにこしたことはないのです。
社労士という労務の専門家の知識がない中で、社長の独断でスタッフの労働条件を決めてしまうと、法律的に問題ある労働条件になってしまうリスクがあります。
また会社設立時は忙しさもあり、先を考えずに労働条件を決めがちです。しかし、一度決めた労働条件は、会社が一方的に低下させることはできません。社労士に相談しておけば、従業員の数が増えたときでも問題になりにくい先を見据えた給与設計が可能です。
このように早い段階で社労士と契約していれば、様々な労務トラブルを未然に防げます。

まとめ

従業員が数名なら、社労士との顧問契約を結ばなくても会社は機能するでしょう。
しかし、会社設立時に社労士と顧問契約をしていない経営者の方も、従業員が5人になった時点で今の体制の確認をおすすめします。
社労士との契約は法律上義務付けはありません。ですが、人事・労務のプロとして、あるいは会社のカルチャーを理解し、よりよくしていくパートナーとして、早い段階から「頼れる社労士」を見つけておくと良いでしょう。
—
いかがでしたか?
社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!
オンラインで完結

個別無料相談を
ご利用ください


執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。